【ゼミ】経済産業省&太陽光発電協会:主力電源化への正念場、2030年までに太陽光発電のFIP比率を25%に引き上げるロードマップ公表 移行促進へ政策と行動計画を議論〔第1回 FIP勉強会〕
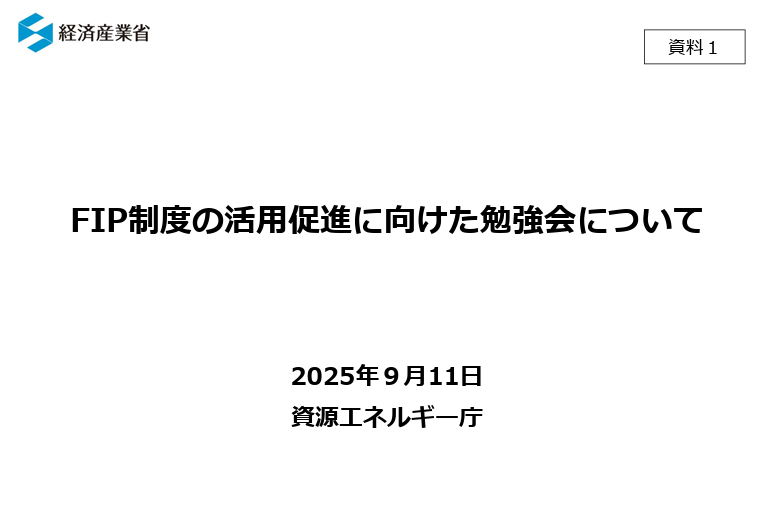
経済産業省・資源エネルギー庁は9月11日、再生可能エネルギーの市場統合を進めるFIP(フィードイン・プレミアム)制度に関する第1回勉強会を開催した。制度導入から3年、FIPの認定容量は3,130MWに達し増加傾向にあるが、総発電容量に占める比率は依然低水準にとどまる。政府は今後、情報開示や蓄電池活用、出力制御ルールの見直しを通じて活用拡大を促す方針。勉強会の後半では太陽光発電協会(JPEA)が、2030年までに太陽光のFIP比率を25%に引き上げるロードマップを公表。官民双方が「脱FIT」加速の覚悟を示した。


■FIP制度とは――FITから市場連動型へ
FIP(Feed-in Premium)制度は、再生可能エネルギーの発電事業者が自ら市場価格を踏まえて電力を販売し、得られた市場収入に一定のプレミアム(補助)を上乗せする仕組み。従来のFIT(固定価格買取制度)が「電力会社が一定価格で買い取る」仕組みであったのに対し、FIPは「市場で売電し、その収入に応じて補助を受ける」制度設計が特徴。
発電事業者は市場価格の変動を意識し、需給バランスや気象状況を踏まえて出力を調整する必要がある。加えて、計画と実績の差(インバランス)を抑制する精緻な発電予測や、価格の低い時間帯に蓄電し高い時間帯に放電するといった運用戦略が求められる。言い換えれば、FIPは再エネを「補助で支えられる電源」から「市場で競争できる電源」へと脱皮させる制度。欧州では既に主流となっており、日本でも2022年度から本格導入された。

■FITからFIPへ「価格シグナル」に対応する新時代
再エネ導入比率は2023年度で23%を超え、拡大は続く。しかしその多くはFIT(固定価格買取制度)によるもので、市場との統合は不十分とされてきた。経産省は「再エネを主力電源とするためには、すべての電源がFIPに移行することが望ましい」との立場を明確にしている。
現状、FIP比率は総量の3%程度にすぎず、とりわけ太陽光では0.8%と極めて低い。だが、制度の成熟とともに市場価格シグナルに基づいた発電・取引の仕組みを確立することが、再エネの自立に不可欠と位置付けられている。

■情報開示と蓄電池活用で投資環境整備
勉強会では、FIP制度をめぐる課題と対応策が提示された。第一に、参照価格や市場データをエリア別・月別に公開することで投資判断の予見性を高める。第二に、蓄電池の活用を制度的に後押しする。系統充電を認め、後設置の際もプレミアム算定ルールを明確化。申請手続きの迅速化を進め、投資インセンティブを強化する。
第三に市場設計の見直しがある。2026年度以降は出力制御の優先順位を「FIT→FIP」の順に改め、需給調整に積極的な電源を優遇する。併せて非FIT証書の取引解禁や企業内融通の拡大により、再エネ価値の多様な流通を認める。政府は「まず25%」という目標を設定し、その間はバランシングコストの交付額を増額してFIP比率の引き上げを後押しする。

■成功事例も登場 予測精度と蓄電運用で収益最大化
FIP制度の実効性を裏付ける事例も出始めた。ある事業者は独自の発電予測システムと蓄電池を組み合わせ、価格が0.01円の時間帯に充電、価格上昇時に供給することで収益を高めた。別の企業は複数の気象データを統合し、新設設備でも高精度予測を実現。国内外の送配電事業者にデータ提供を行うなど、予測技術をビジネス化している。
こうした動きは、FIP事業が「単なる売電」から「市場を前提とした複合ビジネス」へと進化しつつあることを示している。

■JPEAが覚悟表明「FIP比率25%」のロードマップ
勉強会の後半でJPEAは太陽光発電のFIP移行に関するロードマップを示した。2030年までにFIP比率を25%(約23GW)に引き上げるとの目標を掲げた。これは現在の0.8%から一気に30倍以上の拡大を図るものになる。
JPEAは「発電事業者・需要家・金融機関の行動変容が不可欠」と指摘。発電事業者には移行意欲の向上を、需要家には長期安定調達の拡大を、金融機関にはFIP案件への融資枠拡大を求めた。対象は6万5千社の発電事業者、RE100参加93社、再エネ100宣言385社・団体、JCLP229社、全国自治体1,741団体、さらに銀行協会加盟機関まで幅広い。

■2030年「脱FIT」の風景 市場で競う主力電源へ
JPEAは2030年の姿を「FITに依存しない主力電源」と描く。その実現にはPPAの普及、卒FIT電源のリパワリング、調整力市場や容量市場への参入といった新たな収益モデルが欠かせない。政府施策と業界行動計画が同時に動き出したことで、「FIT依存からの自立」は現実味を帯びてきた。
FIP比率25%は単なる数字ではなく、制度移行の通過点にすぎない。日本の再エネ市場は、制度・金融・需要が一体となることで、真に「市場で競う電源」への変革を迫られている。
制度導入から3年、FIPは官主導の制度整備段階を終え、民間主導で市場を切り拓く段階に入った。経産省が政策的な環境整備を進め、JPEAが業界の覚悟を示したことで、双方の役割が重なり合う「官民共闘の第二ステージ」が始まったといえる。
再エネを巡る市場環境は急速に変化している。FIPを軸とした新しい市場設計が定着するかどうかは、今後5年の官民双方の行動にかかっている。

〔参照〕
▷FIP勉強会及びマッチング・プラットフォーム
▷資料1 事務局「FIP制度の活用促進に向けた勉強会について」
▷資料2 太陽光発電協会「FIP移行促進に向けたロードマップ&アクションプラン」
▷ネットライブ中継:第1回FIP勉強会(YouTube)
